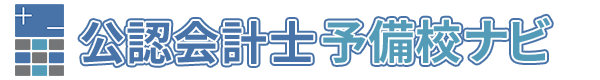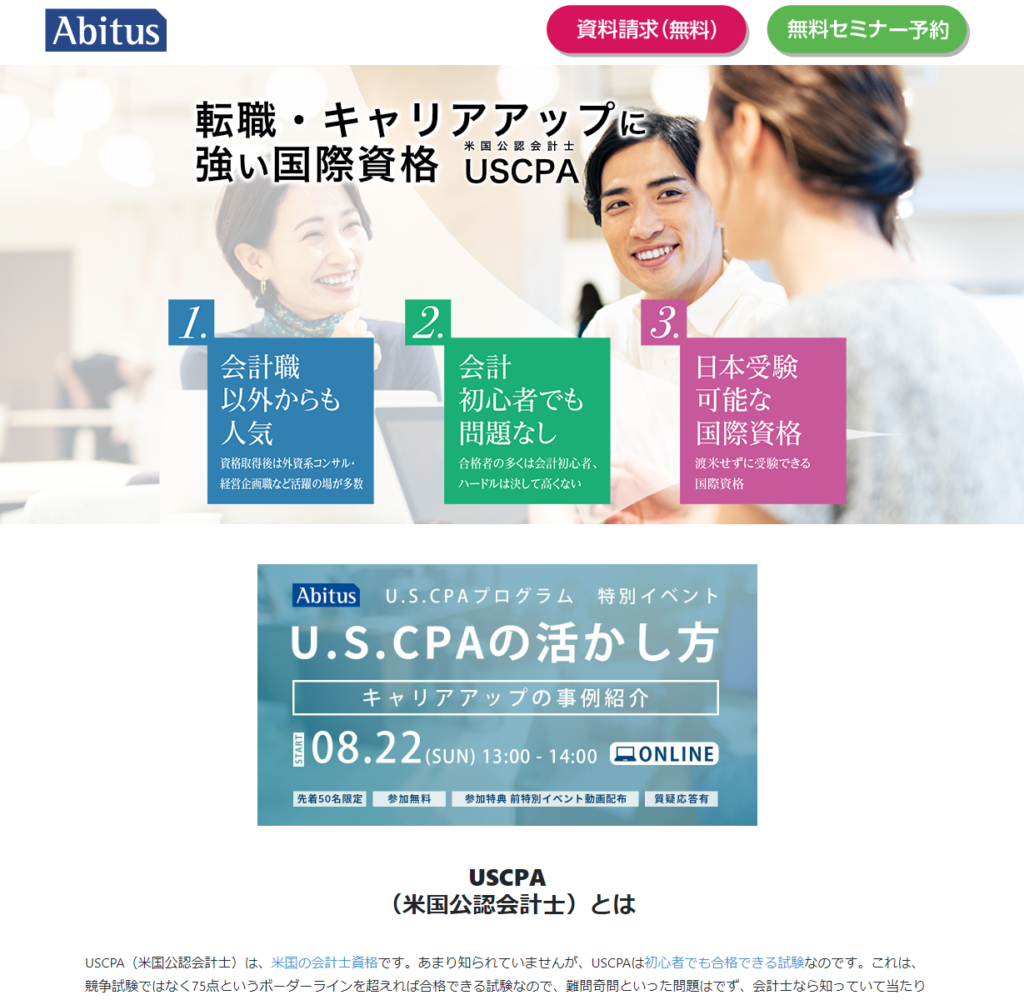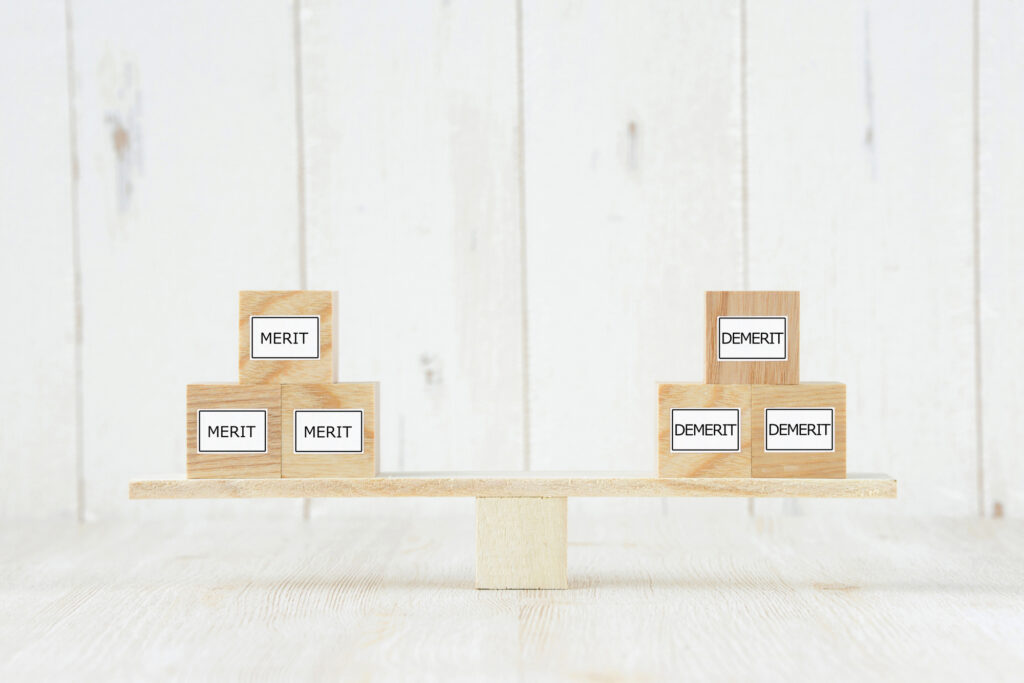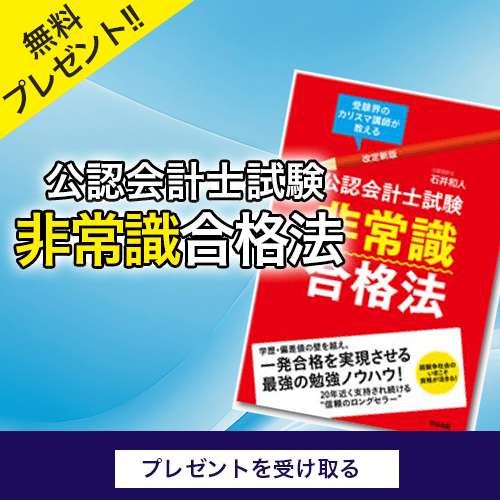公認会計士の試験形式は?内容や試験日程を解説!

もくじ
誰でも受験可能な国家資格「公認会計士」
3大難関資格の一つとして知られる公認会計士。受験に年齢や学歴などの制限はなく、誰でも受験することができます。
会計系資格の中でも最難関といわれており、合格後は高収入や安定したキャリアが期待できる人気の国家資格です。
この記事では、公認会計士試験の制度や試験内容、スケジュールについて最新情報をもとに解説します。
短答式試験と論文式試験の2段階構成
試験制度の特徴
公認会計士試験は短答式試験と論文式試験の2段階で構成されています。
短答式試験の合格者は、その後2年間は論文式試験のみを受験できます。
また、論文式で不合格となっても、一定の基準を満たした科目については「科目合格」として2年間の免除措置があります。
短答式試験は年2回実施され、第1回:12月・第2回:翌年5月に受験できます。
たとえば第1回で不合格になっても、翌年の第2回で再チャレンジできるなど、柔軟な試験スケジュールも魅力です。
短答式試験の内容と試験日程
試験の内容・目的
短答式試験は、マークシート方式の多肢択一形式で実施されます。
主に論文式試験に向けた基礎知識の習得状況を確認することが目的とされています。
出題科目は以下の4科目となります。
・財務会計論
・管理会計論
・監査論
・企業法
合否判定は4科目の総得点で判断されます。
総得点が70%以上であることが合格基準ですが、1科目でも40%未満があると不合格になることがあります。
3大難関資格の一つである、公認会計士。受験資格はとくになく、誰でも受験が可能な資格試験です。会計系資格の最難関資格といわれており、取得すると高収入を得ることができ、安定的な生活を送ることが可能になります。この記事では公認会計士試験の試験制度や科目構成、試験日程などの内容などを紹介します。
短答式試験と論文式試験の2種類がある
■ 試験制度の特徴
公認会計士試験は、受験資格の制限はとくになく誰でも受験が可能です。試験は短答式試験と論文式試験の2種類あります。短答式試験の合格者は論文式試験に不合格になった場合、一部科目で合格基準を超えた科目がある場合、以後2年間はその科目の受験が免除されます。
短答式試験は年に2回実施され(1回目:12月・2回目:翌年の5月)12月の試験が不合格の場合でも翌年の5月の第2回目の試験で再チャレンジすることが可能です(1発で合格される方もいますが、何度かチャレンジして合格する方も多くいます)。
試験日程(令和7年・8年)
| 年度 | 区分 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|
| 令和7年(2025年) | 第Ⅰ回短答式 | 2024年12月8日(日) | 2025年1月17日(金) |
| 第Ⅱ回短答式 | 2025年5月25日(日) | 2025年6月20日(金) | |
| 令和8年(2026年) | 第Ⅰ回短答式 | 2025年12月14日(日) | 2026年1月下旬 |
| 第Ⅱ回短答式 | 2026年5月24日(日) | 2026年6月中旬 |
論文式試験の内容と試験日程
試験の内容・目的
論文式試験は記述式の試験です。
思考力・判断力・論述力を問う問題が出題され、公認会計士に必要な応用力が求められます。
出題科目は、必須4科目+選択1科目の計5科目です。
【必須】
・会計学(財務会計論・管理会計論)
・監査論
・企業法
・租税法
【選択】
・経営学
・経済学
・民法
・統計学
(多くの受験生が経営学を選択)
判定方法は総得点での評価となり、合格基準は52%以上。
ただし、1科目でも40%未満の場合は不合格となる可能性があります。
一部の科目で合格基準を超えていれば「科目合格」となり、次回以降2年間その科目は免除されます。
■ 試験日程(令和7年・8年)
短答式試験の日程は1回目の試験が例年、12月、2回目の試験が翌年の5月。
| 年度 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|
| 令和7年(2025年) | 2025年8月22日(金)~8月24日(日) | 2025年11月21日(金) |
| 令和8年(2026年) | 2026年8月21日(金)~8月23日(日) | 2026年11月中旬 |
合格後の流れ(業務補助等・実務補習)
論文式試験合格後、公認会計士として登録するには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
- 業務補助等:監査法人などで実務経験を2年以上積む
- 実務補習:会計教育研修機構による研修を受講し、単位取得後に終了考査に合格する
監査法人では大学在学中から非常勤勤務できる場合もあり、在学中に実務経験を満たす例もあります。すべての要件を満たすことで、公認会計士として正式に登録されます。
合格発表後から公認会計士に登録されるまで〜業務補助等・実務補習
試験合格後は公認会計士として登録されるために、業務補助等の経験と実務補習を受講します。
『業務補助等』とは、公認会計士登録をするための要件のひとつで、公認会計士または監査法人を補助することや財務に関する監査などの実務に2年以上従事することなどが該当するようです。
『業務補助等』では監査法人に就職することが一般的です。監査法人によっては大学在学中から非常勤として就業できるケースもあります(大学在学中に合格し、そのまま監査法人で2年間働くと業務補助等の経験も在学中に終えることが可能です)。
また、会計教育研修機構が実施する実務補習を受講し規定の単位を取得した方が終了考査を受験し、合格の後に晴れて公認会計士として名簿に登録され、資格を取得が完了となります。
公認会計士試験は科目数も多く対策も難しい試験ですが、短答式試験、論文式試験とそれぞれの特徴や試験制度をしっかり把握、理解することで、効果的な学習スケジュールを立てることが可能になります。
余裕を持って学習期間を長く設定する場合や、一発合格を視野に入れての設定など、各人の環境や状況においての学習計画作りが合格のポイントとなるようです。公認会計士、難関資格ですがチャレンジする価値のある資格のひとつです。
まとめ
公認会計士試験は難関ですが、制度や出題傾向を理解することで、効率的な学習が可能です。
短答式・論文式の仕組みを把握し、自分に合ったスケジュールで挑戦しましょう。
長期的な視野で計画的に取り組めば、合格後には専門職としての大きなキャリアチャンスが開かれます。